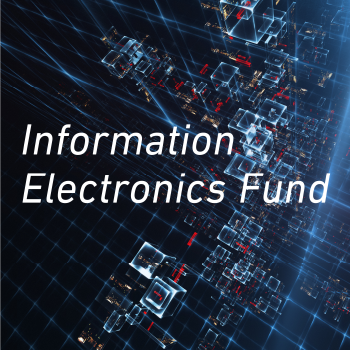福田コメント
"長期投資"は絶対でしょうか?
サブプライムローン問題などによる信用不安がベアー・スターンズ、リーマン・ブラザーズの実質的な経営破綻に発展し、"100年に一度"の経済危機と言われた2008年以降、事態の深刻化に対応して異例の金融緩和政策が世界中で断続的に導入されました。こうした非伝統的な金融緩和政策などが功を奏し、世界の株式市場は2010年代を通してグロース株を強力なリード役とした上昇基調を辿りました。特に、2014年にECB、2016年に日本銀行がマイナス金利政策を導入してからは、グロース株が買われる傾向がさらに強まりました。また、まるで"債券代替投資"かのように低ボラティリティな株式を"まだ利回りが残っている債券(に近い株式)"と見做し、バリュー株のうち高配当株を対象としたイールド・ハンティング(利回り追求)目的の、一種のキャリートレードが流行するといった、金融緩和政策がもたらした副作用としての行き過ぎた投資が目立ち始めたように思います。その後、新型コロナウイルスの蔓延に対応した追加的な金融緩和政策をクライマックスとして、長期グロース株投資ブームがついに終焉を迎え、過去2~3年間は世界的に金利が反転・上昇に転じたことなどを受け、企業価値が遠い将来のCF(キャッシュフロー)の割引現在価値に大きく左右されるため割引率(リスクフリーレート)の影響をより強く受けるグロース株投資は厳しい投資リターンが続いていると見ています。
私は上記の期間、2011年4月以前は日本の年金基金の、以降は日本の公募投資信託のファンド・マネージャーとして、日本の株式市場でアクティブ運用にあたってきましたが、2010年代以降、グロース株投資と"長期投資"が混同されるようになってしまったと感じています。
本来、"長期投資"というのは、「GDPや企業収益など経済成長の果実はゼロサムゲームでなくプラスの付加価値が長期的には高い確率で期待できるため、長期的な視点で株式市場に参加し続けていないとその果実を得られない恐れがある」という趣旨であり、主として最終投資家にとっての資産配分の問題でした。ところが今では、米著名投資家が実践されてきたような株式市場における、長期的に市場平均を上回るリターンを出し続けるための投資哲学と誤解されている方が多いのではないでしょうか?
本来、投資というものは投資対象が株式であれ債券であれ、はたまた設備投資であれ、一定期間における投資効率で有効性が評価される限り、より短い期間でより高いリターンが得られるのが良い投資だと私は考えます。ただ、世の中そんなに簡単に高いリターンが得られる投資機会が数多く存在するほど非効率的だと想定するのは現実的ではなく、投資してその投資金額を回収するまでの期間、ある程度のリスクを負担することになるわけです。ここで重要なのは結局のところ、長期投資であるかどうかではなく、有望な投資対象を見抜き、適切なタイミングでリスクを取って投資を実行する能力であり、それを実践するのに結果としてある程度長い時間が必要である、というに過ぎません。優れた洞察力、知性を持つウォーレン・バフェット氏とチャーリー・マンガー氏の名コンビをもってしても、総じて言えば、高いリターンが見込まれる投資機会を見つけ、投資し、リターンを実際に得るのに長期間が必要だったということです。
×)"長期投資" → 成功する投資、企業と目線を合わせた良い投資
〇)"長期投資" → 効率良くリターンを得るための投資(できるだけ早期に高いリターンを得ようとした結果として投資期間が長期に)
前者ではなく後者が、私が考える正しい因果関係だと思います。