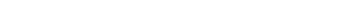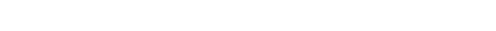お知らせ
「相互関税」を受けた各市場の見通しについて
2025年04月07日
グローバル株式市場、日本株式市場、債券市場・為替市場それぞれの今後の見通しについて、当社からのメッセージをお知らせいたします。
■グローバル株式市場について
米国株式市場は4月2日の米トランプ大統領による相互関税の発表をきっかけに、3日、4日の両日で10%超の下落となりました。
米トランプ大統領が4月2日に公表した関税政策は、全ての輸入品に一律10%の基本関税を課したうえで、各国の関税や非関税障壁等を考慮し、それぞれの国や地域に相互関税を上乗せするものとなりました。上乗せされた税率は日本が24%、EU(欧州連合)が20%、中国が発動済みの関税を含めて54%となるなど、市場参加者が予想していた内容よりも高いものとなりました。このような政策に反発して、EUや中国は米国からの輸入品に対する報復関税を課す方針を示しており、貿易戦争が深刻化する懸念が高まったことが株価下落の幅を大きくしています。
貿易赤字の縮小を目的として米国が発表した相互関税は、このまま適用されれば実効関税率を20%台半ばまで上昇させることとなり、戦後最も高い水準になるものと見られます。こうした高水準の関税は輸入品の値上がりを通じて米家計の消費を減少させ、景気悪化をもたらす可能性が高まっています。米トランプ大統領が「米国は全く違った国になる」と発言しているように、これまで構築してきたグローバルサプライチェーンを大きく修正する必要に迫られることから、広範な影響が懸念されます。一方で、米トランプ大統領が「軽減につながる交渉にはオープン」であると発言している通り、今後、各国との交渉の結果次第では関税率が引き下げられる可能性があると見ています。また、こうした関税を財源として、所得税減税の延長や法人税の引き下げ等が進めば一定程度の景気浮揚効果があるものと見られます。
今後の市場動向を判断する上で2025年の企業業績動向が重要になると考えています。S&P500をベースとした集計では、2025年通期は依然+11%程度の増益予想となっています。この予想通りであれば、S&P500指数のバリュエーション(投資価値評価)は昨年末時点の25倍程度から19倍程度まで調整してきた事になります。しかしながら、現段階では相互関税の影響を、業績予想に織り込めていない状況であり、現在の増益予想は低下していく可能性が高いと見ています。仮に0%成長(前年同水準の利益)と仮定すると、一株当たり利益では243ドル程度ですので、PER20倍程度を許容してもS&P500指数は4,800~4,900という計算になります。また、各企業が相互関税の影響を見極める事が難しい状況は、例年に比べて企業業績予想の信頼度が低いという事になりますので、予想の信頼度が低いこと自体が短期的にはバリュエーションの低下要因もしくはボラティリティの上昇要因となり得ます。関税政策そのものや、その影響をうける企業業績が大きく変化しうる状況のなかで、引き続き変動率の高い相場環境が継続するものと予想されます。
また、FRB(米連邦準備制度理事会)の動きにも注目が集まります。FRBのパウエル議長は4月4日の講演で、様子見姿勢を続けるスタンスを示しました。しかしながら、関税政策によってこれまで堅調に推移してきた米国の雇用市場は減速する可能性が高いこと、加えて足元の株式市場の下落が逆資産効果を通じて米国の個人消費を冷え込ませる可能性を踏まえると、FRBは関税によるインフレ高進を警戒しつつも、雇用市場の減速や景気の低迷を受けて利下げに追い込まれる可能性もあると見ており、引き続きFRBの動向にも注意してまいります。
各国の関税政策や金融政策、企業業績動向を注視しながら、関税の影響が相対的に小さいと考えられる銘柄や、不透明な経済環境下でも継続的な需要拡大が見込まれる銘柄等については、株価の下落によって割安となったバリュエーションを捉えてパフォーマンス向上につなげていきたいと考えています。
CIO(グローバルアクティブ)
中山 貴裕
■日本株式市場について
本日4月7日の日本株式市場は大幅続落となりました。日経平均株価は、昨年安値である31,458円(2024年8月5日)を割り込み、関税の影響の深刻さを露呈しています。
一時的なイベント等による急落であれば短期的に戻りを試すことも多いのが相場のよくあるパターンですが、今回はマクロ、ミクロの想定以上の不透明感が急浮上しており、また今後の現実的な影響度を図ることも難しい状況であることから、当面は一定のボラティリティの中で現状程度のレンジ推移となると思われます。
なお本日の下落でTOPIXベースのPERは約12倍まで低下しています。リーマンショック以降でPERが12倍程度まで低下したのは、東日本大震災、第2次安倍政権前の政局混乱期、チャイナショック、コロナ禍初期等の限られた局面しかありません。これを鑑みますと、足元の株価下落で米トランプ政権の関税政策による一連の混乱を織り込んだのではないかとの見方も出来ます。ただしこれらの低PER局面では世界経済全体が大きく傾くような情勢にはなっていない、または一時的な混乱によるものでその後の回復も早いという状況であったと思いますが、今回は米国経済自体も返り血を浴びて減速する可能性が増してきているため、今後は関税の影響だけでなく世界経済減速の影響をどこまで織り込むのかという視点も重要となってきています。したがって、現在PER12倍まで低下したという認識が、業績の下方修正を織り込むとまだ下落する懸念があるというような見方も出来なくはありません。
今回の関税の影響は、単に関税によって最終価格の値上げを余儀なくされる、あるいは最終価格を維持するために企業側がそのコストを飲み込むということだけに限りません。自由貿易体制、最適地生産で経済拡大を享受してきた世界経済運営自体の見直しが必要となる、あるいは企業ベースでは経済の不透明感から投資を抑制する等の行動が見られる可能性があります。今般の相互関税を受けての米国と各国の交渉状況、またそれを踏まえてのグローバル経済の方向性、このあたりの見方が何らか出てくるまでは市場環境も不透明感が拭えず、当面株価も頭の重い展開となると考えます。
このような環境にあっても、相対的に業績を維持できる銘柄、関税の影響を受けにくい銘柄も存在します。また影響を免れることは出来ないものの中長期の実力を勘案すると割安感のある銘柄なども出てくる可能性が高いと思われます。不透明な環境下でこそアクティブの銘柄選択の腕の見せ所であり、ファンドパフォーマンスの保全に努めて参ります。
CIO(日本株アクティブ)
原田 信太郎
■債券市場・為替市場について
先週、債券市場では日米の国債利回りが大きく低下し、為替市場では円高が進行しました。
米トランプ大統領による相互関税が発表されたことを受け、中国からは追加関税やレアアースの輸出制限などの報復措置が発表され、欧州連合(EU)でも米国の大手テクノロジー企業に打撃を与える措置を含む幅広い対抗策が協議されていますが、今のところ米トランプ大統領から関税措置を緩和する姿勢は示されていない状況です。
足元の為替市場では、ユーロや円が米ドルに対して上昇した一方で、豪ドルなどの資源国通貨や新興国通貨が米ドルに対して下落してきました。本日4月7日時点では、一時1米ドル=145円を割れるなど、多くの通貨に対して円高が進行しています。
今後の為替市場については、全体として主要通貨に対して米ドル安の動きが続きやすく、円についても米ドルに対して上昇(円高)が続くと考えています。
為替市場の決定要因の一つである金融政策の観点からは、FRBが利下げ再開に舵を切る可能性が高まっていると考えており、米ドルが下落しやすいと見ています。パウエル議長は4月4日の講演で、様子見姿勢を続けるスタンスを示しました。しかしながら、関税政策によってこれまで堅調に推移してきた米国の雇用市場は減速する可能性が高いこと、加えて足元の株式市場の大幅な下落が逆資産効果を通じて米国の個人消費を冷え込ませることを踏まえると、FRBは関税によるインフレ高進を警戒しつつも、雇用市場の減速や景気の低迷を受けて利下げに追い込まれると考えられます。そして、FRBによる利下げを受けて、為替市場では円やユーロなど主要通貨に対して米ドルが下落に向かうと見ています。特に株式市場の下落などリスク回避的な動きが続く場合には、円高が継続しやすいと考えています。
加えて、米国の関税政策の転換が、長い目で見て米ドルの下落圧力となる可能性に注目しています。経常収支赤字国の米国は海外からの資金還流に依存してきましたが、今後、国際的な貿易や金融取引が縮小してしまう場合には、米ドルが下落しやすくなるリスクがあると考えています。
米国債市場では、米国10年国債利回りは先週4月4日に一時的に3.85%まで低下し、昨年(2024年)10月上旬以来の水準となりました。今後、FRBの利下げ再開や、関税による景気への悪影響を示す経済指標が徐々に見えてくるにつれて、米国債利回りは引き続き低下しやすい状況であると考えています。特に利下げ織り込みの進展に伴い、短期年限の債券利回りが相対的に低下しやすく、イールドカーブはスティープ化しやすいと想定しています。
国内債券市場でも、世界経済の先行き不透明感の高まりを背景に大幅な金利低下が生じています。日銀の利上げ期待から日本10年国債利回りは3月下旬に一時1.60%近傍まで上昇していましたが、足元では1.05%程度での推移となっています(本日4月7日9時時点)。日本に課せられる関税が24%と当初想定を上回る高税率となったことで、日本経済へのマイナス影響も相応に懸念されるところですが、国内の人手不足に伴う賃金上昇圧力が高まっている状況下、現状の政策金利水準が相応に低いことに鑑みれば、日銀は引き続き追加利上げを模索していくものと考えています。市場は当面ボラタイルな変動を継続すると考えますが、日銀が先行き追加利上げを実施することを勘案すれば、10年国債利回りが1%を下回って推移する展開は想定し難く、次第に水準を切り上げて安定化していくものと見込んでいます。
不確実性が意識される市場環境の中、様々な投資機会をとらえてパフォーマンスの向上に努めて参ります。
債券戦略委員会委員長
前田 有司
- 当資料は情報の提供を目的としており、当資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
- 当資料に掲載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。
- 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。